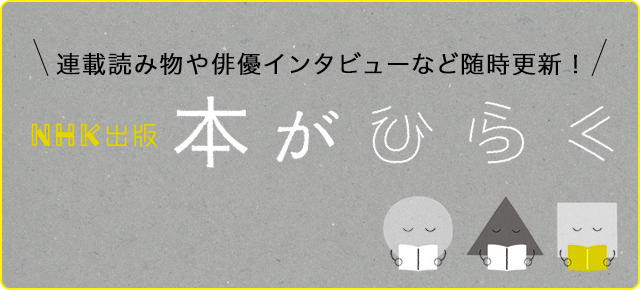同世代の多くの男性と同じように、彼も第一次世界大戦がはじまると、従軍することを強く望むようになります。戦争という刺激的な体験を経ることによって、一人前の男、立派な人間になろうと考える。とこが、左目が弱視でアメリカ軍の基準に達しなかったため、従軍できなかった。ヘミングウェイは仕方なく赤十字に応募して、一九一八年、イタリア軍付赤十字で野戦病院の救急車を運転することになります。彼が書いた短篇のなかに、看護師をたくさん乗せて救急車を運転していたら敵地に紛れ込んでしまう場面が出てきますが、ヘミングウェイは実人生で同じような失敗を何度も経験していたようです。救急車を運転しているときに敵の砲弾を食らい、身体に破片が二〇〇個も食い込む大怪我をする。そして、生死の境をさまよったこの入院時に、自分の世話をしてくれた女性の看護師と恋に落ちる。ところが、結婚を申し込んだら断られてしまったのですね。この体験が、後に『武器よさらば』に活かされたと言われています。
第一次世界大戦が終わってアメリカ合衆国に帰国すると、ヘミングウェイはシカゴでシャーウッド・アンダソンと知り合い、影響を受けるようになります。そして一九二一年にはパリに渡り、ガートルード・スタイン、ジェイムズ・ジョイス、エズラ・パウンド等、モダニズム文学の旗手たちと知己を得、パリで文章修業をする。はじめのうちは『トロント・スター』紙というカナダの新聞社の特派員というかたちでパリに滞在できる状況をつくって、特に短篇小説を精力的に書く。それほどお金がないなかで、いくつものカフェを転々としながら小説の修業をしていたこの時期の様子は、ヘミングウェイの死後に出版された『移動祝祭日』に詳述されています。
一九二四年の短篇集『われらの時代に』で注目を集めた後、長篇『日はまた昇る』で多くの読者を獲得し有名になります。この作品は、ざっくりいうとアメリカからパリにやってきた芸術家志望の若者たちの自堕落な生活と、闘牛についての話です。フィッツジェラルドの回で見たように、第一次世界大戦後、芸術家志望だけれど金も仕事もないというアメリカの若者たちはパリに集まる。そこで、刺激や愛を求めるが、なかなかうまくいかない。そんななか、皆でスペインに闘牛を見に行くことになり、自分の命を懸けて牛とギリギリの闘いをする闘牛士の姿に生きる意味を見いだす、というストーリーです。この作品を書くことで、自分の意志でいかに死に近づけるかということが、生きている実感を持てる唯一の倫理的なことである、というヘミングウェイ一流の思想がかたちづくられていきます。
一九二九年の『武器よさらば』では、第一次世界大戦における戦争の悲惨さや、女性看護師との恋を描きました。この作品のなかでは愛を受け容れてもらい、逃げ出した先のスイスで子どもを持とうとするのですが、看護師は死んでしまうという悲劇的な展開をします。『誰がために鐘は鳴る』は、スペイン内戦でファシストとの戦いに身を投じた主人公が、戦略上重要な橋を爆破し、負傷しながらも仲間を逃して息絶える物語です。自分が死んでも皆が自由に生きられる社会ができるならそれでいい、という話で、これはヘミングウェイ自身が共産主義者とともにスペイン内戦に参加したあとで書かれた作品です。
そして一九五二年、『老人と海』でピュリッツァー賞を獲ります。キューバの漁民であるサンチャゴという老人が、格闘の末に巨大なカジキを釣り上げるけれども、カジキはサメに食われて結局骨だけになっちゃうという話なんですが、老いても自分の命を懸けて正々堂々と闘って負けていく様は、それ自体素晴らしい、美しいものなのではないかと感じさせる。これで晩年に大きく評価を上げて、ノーベル文学賞まで獲得します。
作家としては順調だったヘミングウェイですが、実人生では度重なる怪我に悩まされ、飛行機事故にも何度も遭う。心身ともにボロボロになり、電気ショック療法など、さまざまな治療を受けるんですが、最後は持病の鬱が悪化して、一九六一年に猟銃自殺してしまいます。
二者間の対決と死のモチーフ
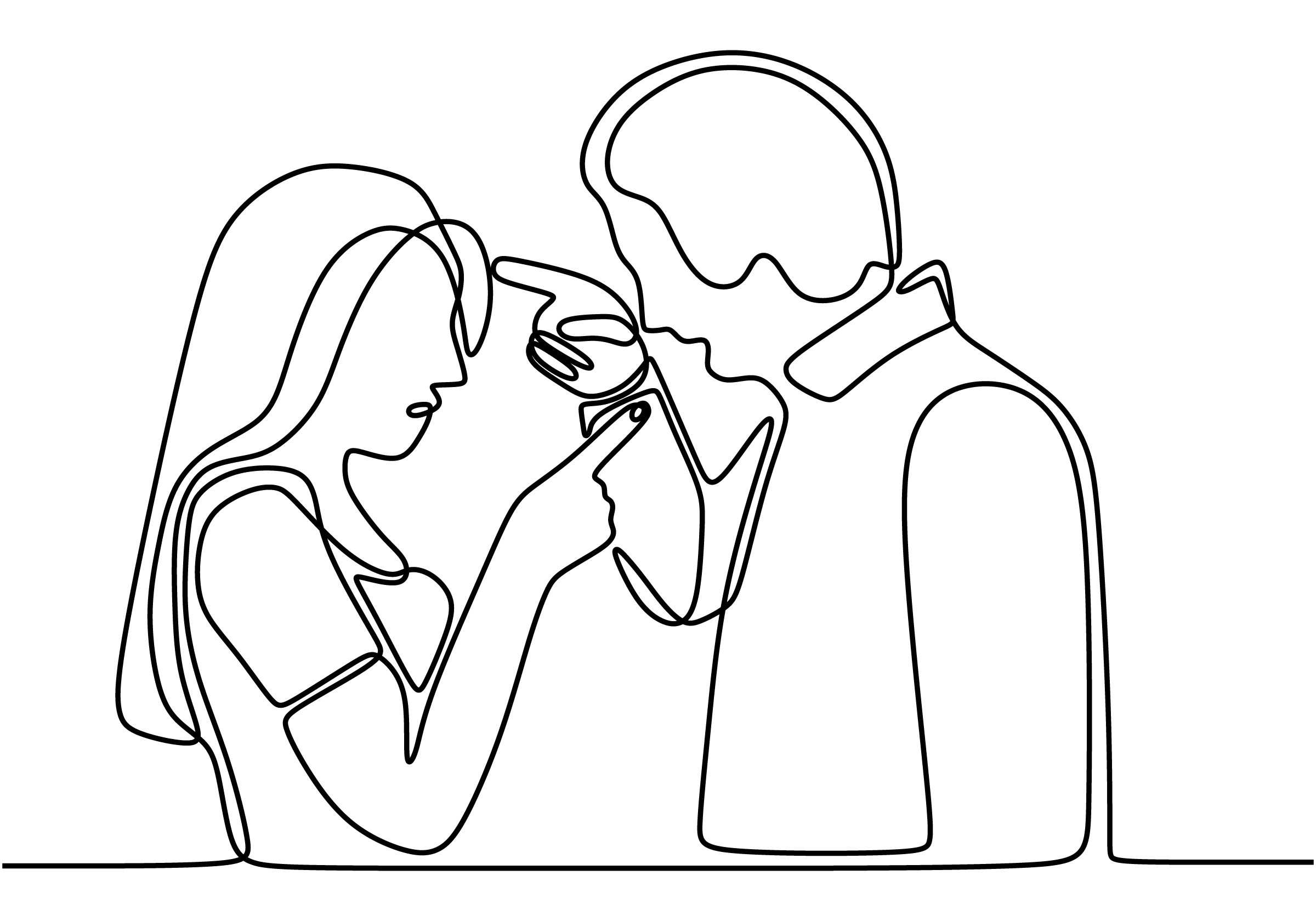
「白い象のような山並み」は非常に短いので明らかにされていないことも多いのですが、この作品の背景について考えていきます。一九二七年という発表年を考慮すると、時代としてはおそらく一九二〇年代、第一次世界大戦と第二次世界大戦の狭間の時期だと思われます。人物の設定は、前年に発表された『日はまた昇る』に近い。アメリカ人の若者がスペインに行って人間関係のすれ違いを経験します。
結局、男性のほうは、きちんと女性と結婚して、責任を持った大人の生活に入っていくのが嫌なんですよね。大人になりたくない、責任を取りたくない、将来どうなるか見えてしまうような暮らしはまっぴら御だ、みたいに思っている。女性のほうは、「こんな生活が続くわけないだろう、私も妊娠したし、もう少しちゃんと人生を考えなさい」と思っている。しかし男性は考えない。よくあるといえばよくある、しかしながら、アメリカ文学にとってかなり重要なテーマを扱っています。マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』などをはじめとして、きちんと生きろと迫る女性と、そこから逃げようとする男性を描いた作品は多いです。
それと同時に、二者間の「つばぜり合い」が、ヘミングウェイの作品にはよく出てくる。『男だけの世界』という短篇集の冒頭には、「敗れざる者」という中篇くらいの長さの作品が収録されています。これは、老齢の闘牛士マヌエルが、凶暴な牛に殺されそうになりながら、最後の最後になんとか牛を倒すという話です。また『老人と海』でも、漁師とカジキが格闘する。男性とつばぜり合いを演じる相手として、女性と牛とカジキを全部いっしょくたにしてしまうのも、それはそれでどうかという気もするんですけれども、いずれにしても、ヘミングウェイのなかに、他者と敵対することによって初めて人生の意味というか、面白みというか、意義のようなものが輝くという発想があるので、こういう作品が多く書かれているのではないかと感じます。
「白い象のような山並み」は、女性の側からすれば、もっともらしいことは言うけれども全然人の話を聞いてくれない、全然分かってくれない男性のずるさみたいなものが見える、とてもうまくできている作品だと思います。ヘミングウェイは、マッチョな部分もあるけれどもマッチョの限界も書いているし、男っぽさの魅力の話をしながら、魅力的な男性のダメさも見えるように書く。実は、常に両面から読める複雑な作家なのではないか。
対立の果てに死がほの見えてきて、そのことによって生きていることを痛烈に感じるという展開は、おそらくヘミングウェイ自身の戦争体験を反映している。「ロスト・ジェネレーション」は戦争と関係があるという話をしましたが、戦場で生死の境をさまようほどの負傷をした彼にとって、それは強いトラウマ的な経験だったと思うのです。にもかかわらず、生きのびた後も、危険なハンティングをするとか、従軍記者となって記事を書くとか、死と隣り合わせになるような無茶な場面に飛びこんでいく。こういう言い方をすると「ただの病気」と言っているように思われるかもしれませんが、ある種、トラウマ的な経験を自主的に反復しながら作品を書いたのかもしれません。危険な場所に身を置き続けることが単に芸術のため、作品に迫真性を与えるためだけでもないように感じられるのもヘミングウェイという人の面白いところです。
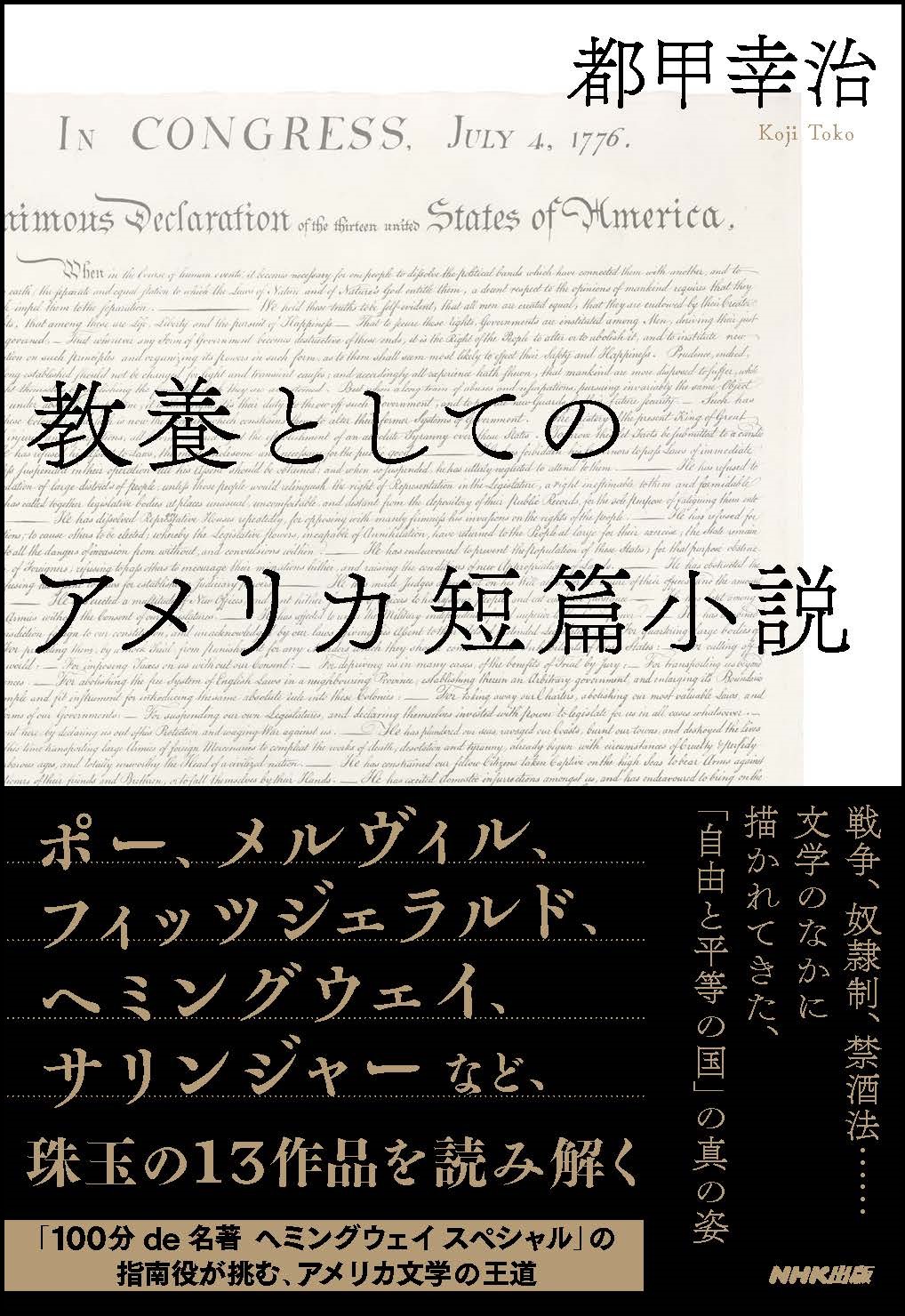
「教養としてのアメリカ短篇小説」