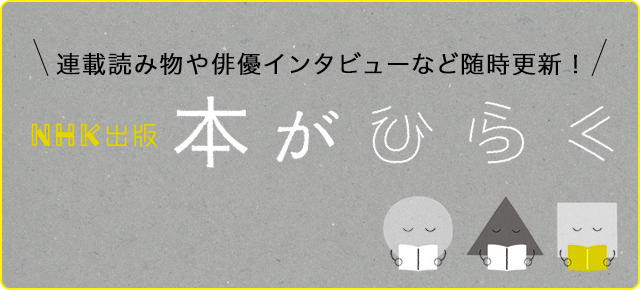多言語で構築された世界

それでは作品の細かい部分を検討していきましょう。まず考えてみたいのは言語のことです。舞台はスペインで、メインの登場人物がアメリカ人なので、ここではスペイン語と英語という二つの言語が話されているはずです。原文ではどうなっているかというと、作品は基本的に英語で書かれています。日本語訳ではわかりませんが、男がスペイン人の店員に話しかける言葉やスペイン人の発言も、ほとんどがあらかじめ英語に訳された状態で読者に提示されている。
このことはどのような効果を生んでいるのか。まず、登場人物の男女のあいだには、スペイン語に対する理解度の違いがある。男はスペイン語で会話したり、メニューを読んだりできる。女のほうは、「あの上に何か書いてあるわ。なんて書いてあるの?」とか、「ねえ、何て言ったの?」というふうに、スペイン語がほとんど分からない。「ドス・セルベサス(ビールを二つ)」というかんたんな単語の部分だけはスペイン語でそのまま書かれていたりします。
これはヘミングウェイがよく使う手法で、『老人と海』も舞台はキューバで、基本的には全編スペイン語の会話なんですが、小説はすべて英語に訳した形で書かれる。小説の終わり近くに唯一、アメリカから来た観光客が英語で話す場面があります。スペイン語が分からないために、彼らは、ある誤解を抱えたまま立ち去る。そのことが読者には分かるという構造になっている。
「白い象のような山並み」でも、女性のほうは結局、スペインの人たちが何をやっているのかよくわからないまま、いまひとつ信用ならない男に左右される状況に置かれる。外国で、自分が理解できない言葉をす人たちのなかにいるときの感覚が再現されている。そして、現地の言葉ができる人、ここでは男のほうが、できない人、女よりも圧倒的に優位に立つ感じなども、本当にうまく描き出されています。女性の疎外された立場、というふうに言ってみてもいいかもしれないんですが、アメリカ文学のなかに他言語や翻訳がどのように出てくるかということを考えるうえでも重要なサンプルではないかと思います。
もう一点、これはタイトルになっている「白い象のような山並み」に関連する会話から考えたいことがありまして、その部分を見てみましょう。
「あの山並み、白い象みたい」彼女は言った。
「白い象なんて、一度も見たことないな」男はビールを飲んだ。
「ええ、ないでしょうね、あなたは」
「いや、あるかもしれないぞ」男は言った。「おれが見たことないときみが言ったからって、そのとおりとは限らないんだ」
高見浩訳「白い象のような山並み」(『ヘミングウェイ全短編1 われらの時代・男だけの世界』所収、新潮文庫。以下、引用はすべて同様)
これは男女の会話の最初のほうに出てくるやりとりです。女からすればめちゃくちゃ気に障るいちゃもんをつけられて嫌な気分だと思うのですが、景色が「白い象みたい」だという何気ない会話のなかにも、この後の男の一種暴力的な、卑劣な言葉の使い方が予告されている。
まず、「おれが見たことないときみが言ったからって、そのとおりとは限らないんだ」という台詞がすごい。もはや実際に見たことがあるかないかも関係ない。論理のハラスメントというか、もはや論理的に成立しているのか怪しいですが、「女の言ったことを受け容れるつもりはないし、全部理屈で言い負かしてやる」という男の決意表明のようなものを感じます。
巧妙なダブルバインド
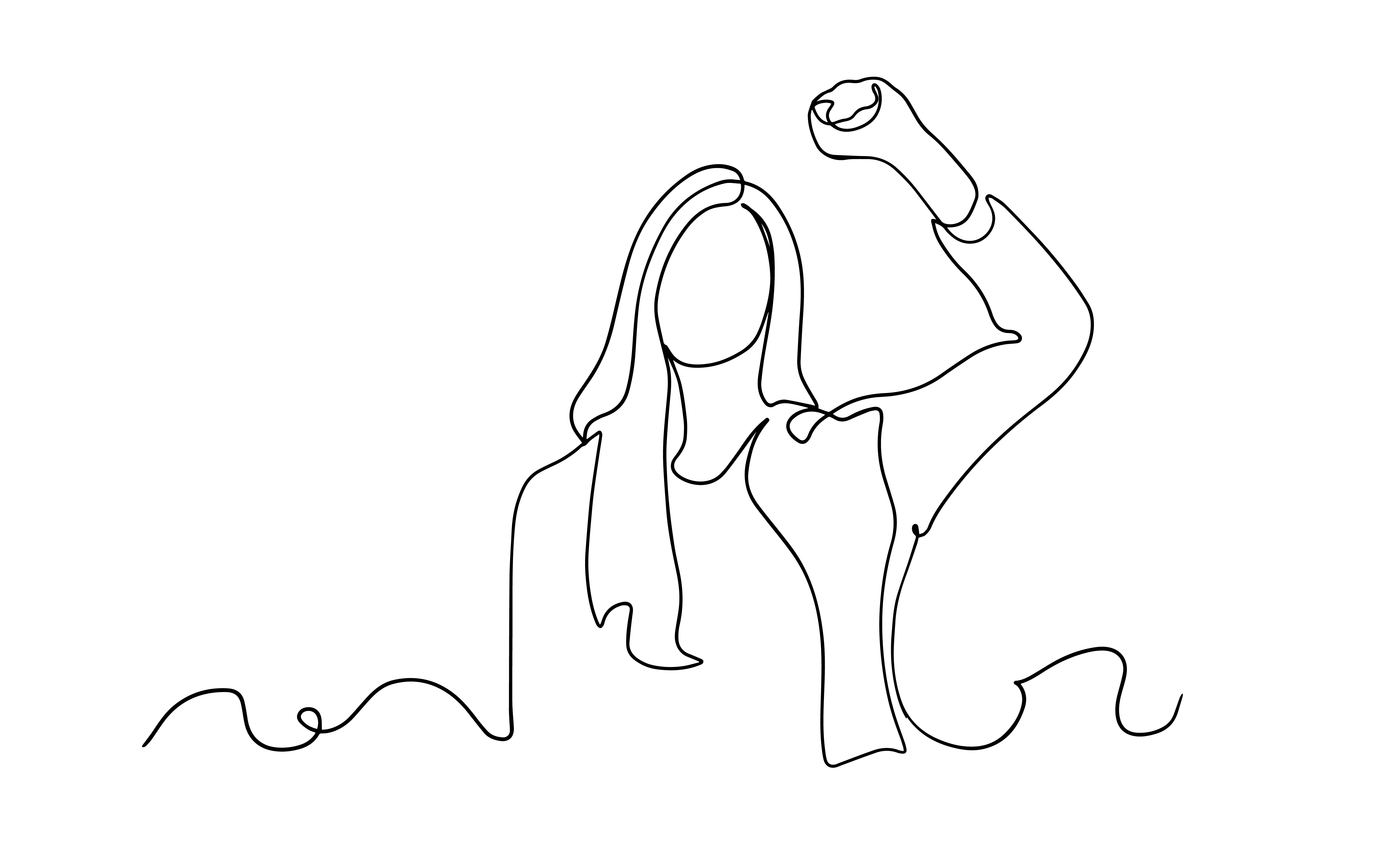
男はこのあと、女の言葉をできるだけ否定しながら、しかし堕胎については女が自分から言い出すように誘導しようとする。実際の会話の流れを見てみましょう。
「本当に、ごく簡単な手術なんだよ、ジグ」男が言った。「手術なんて言えないくらいさ」
若い女は、テーブルの足元の地面を見た。
「きみだって、平気だと思うよ、ジグ。本当に、どうってことないんだから。ただ、空気を入れるだけなんだから」
若い女は何も言わなかった。
「おれも付き添っていくよ。終るまでずっと一緒にいるから。ちょっと空気を入れるだけで、そのあとはまったく自然にもどるんだから」
「じゃあ、それからどうなるの、あたしたち?」
「そのあとは、素敵な関係を保てるさ。以前みたいに」
「どうしてそう思うの?」
「だって、いま二人の頭にひっかかってるのはそれだけだろう。それがあるから、おれたち、気がふさいでるんじゃないか」
まず男が「めちゃくちゃに簡単な手術で、ちょっと空気を入れるだけ」とか言い出すんですが、そんなわけないんです。そんなわけないと、この場所にいる全員が知っているのに、言う。そして、「いま二人の頭にひっかかってるのはそれだけだろう。それがあるから、おれたち、気がふさいでるんじゃないか」。「それ」は原文ではthe only thing で、彼女のお腹のなかの赤ん坊をモノ扱いしている。こういったところにも注目したいですね。
「だから」男は言った。「気が進まないなら、やらなくていいんだ。きみがやりたくないのに、無理にやらせるつもりはないさ。でも、拍子抜けするほど簡単なんだから」
「で、あなたは本当にそうしてほしいわけね?」
「それが最善の策だろうな。でも、きみが乗り気がしないなら、無理してやらなくたっていいよ」
「もしあたしがやれば、あなたの機嫌が直るし、すべては元通りになって、あたしを愛してくれるわけね?」
「いまだって愛してるさ。わかってるだろう、それは」
「ええ、わかってるわ。でも、もしあたしがやれば、何かが白い象みたいだってあたしが言っても楽しくなって、あなたも気に入ってくれるのね?」
「ああ、気に入るとも。いまだって気に入ってるけど、そっちに頭がいかないだけだよ。悩み事があるとおれがどうなるか、わかってるだろう?」
「嫌なら手術を受けなくていいよ、必要ないんだから」と言う一方で、同時に、手術を受ければもっと関係がよくなるとも言う。「手術を受けた場合、関係が改善する」という言葉は、暗に「手術を受けなかった場合、関係は悪化する」ことを意味していますよね。「最悪の場合、俺はお前を捨てるけど、いいのか?」と言っているのと同じです。「手術を受けなくていい」と、「手術を受けなかった場合、関係は悪化する」は、説得としては矛盾している。矛盾したメッセージで両側から締め付けて、なんとか女に自発的に「わたしは子どもを堕ろします」と言わせようとしている。これは人をいちばん苛立たせる、不誠実きわまりない態度だと思います。
しかも、この話をしているスペインも、隣接しているポルトガルもフランスも、カトリックの国です。当時、堕胎は違法ですから、男はおそらく非合法な手段で堕胎させようとしている。そんな手術を受けた後に、二人の関係が元に戻るとか、今までより良くなるなんてありえない。女はそれを分かっているし、男も本当は分かっているのですが、「二人の関係は変わらないし、むしろもっと幸せになれるんだ」などと言う。この部分、あまりに無理な論理展開なので、女を説得しようとしているというよりも、男が必死で現実を否定するために自分に言い聞かせているようにも読めます。女は賢いので男の意図は即座に見抜いて、その手には乗らない。
「じゃあ、やるわ。あたしなんか、どうなってもいいんだから」
「どういう意味だい?」
「あたしなんか、どうなったっていいのよ」
「いや、よくないよ」
「ええ、あなたはね。でも、あたしは、どうなったっていいの。だから、やるわ。それで、何もかもうまくいくんだから」
「そういう気持でいるなら、やらないでほしいな」
ここは女の側が仕掛けている場面ですね。「私は自分自身がどうなっても構わないし、下手したら死ぬかもしれないけど、それでも構わない。自分の意志なんて関係ない。というか、もっと言うと自分の意志なんてないからやる」と言うことによって、「自分にとっては自分の命なんてどうなってもいいし、自分の意志なんてないから、あなたの言うようにします」、イコール「自分の意志のない私はあなたに命令されてやるだけなので、関係が悪化したらあなたのせいだし、もし手術で体調が悪化して死んだりしたら一生後悔させてやる」と男に伝えている。
決定的なことを直接言わないように、躱かわしあいながら、しかし互いを追い詰めていく。その緊張感がよくわかるので、スリリングなものとして読んでいけるのではないかと思います。
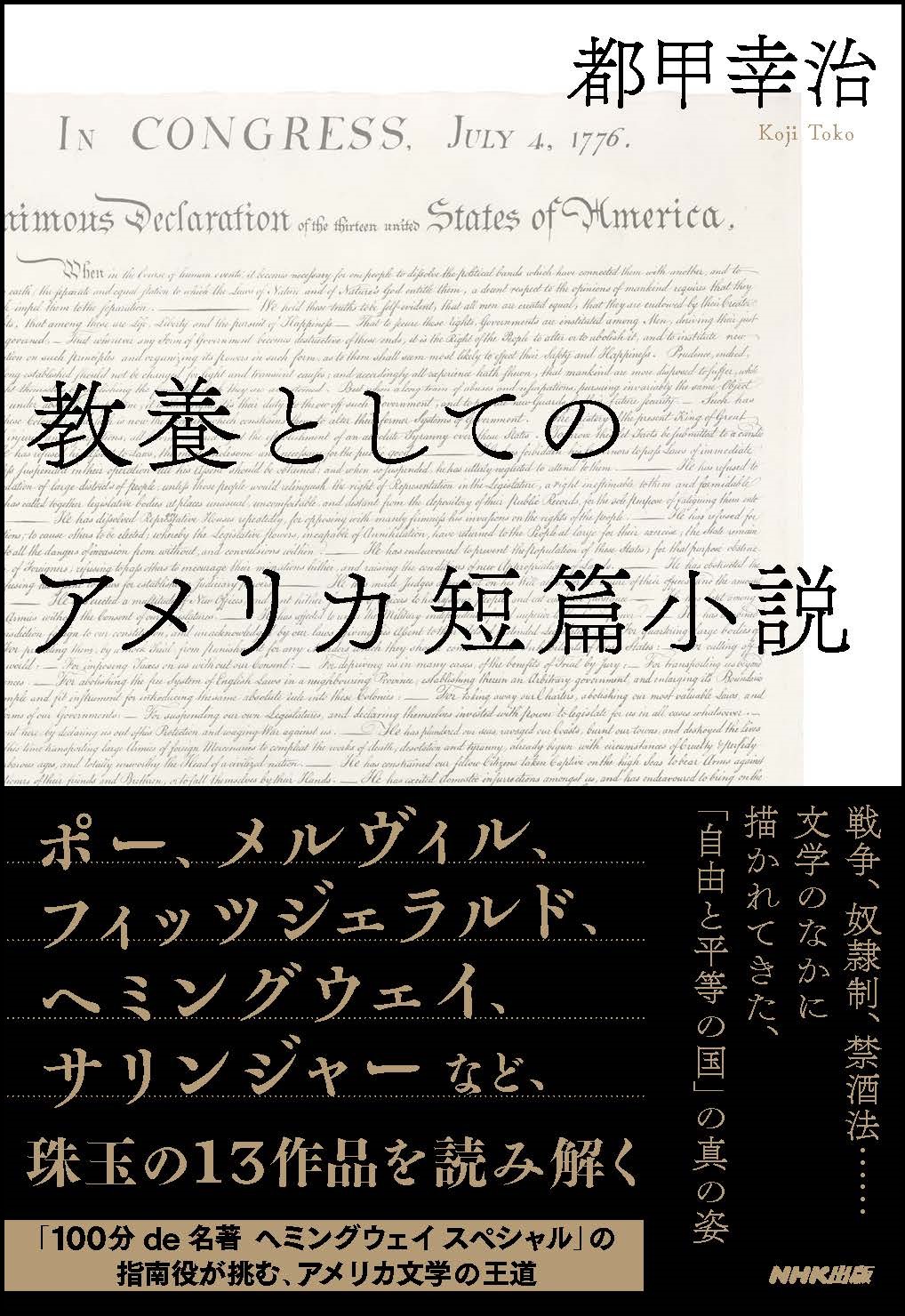
「教養としてのアメリカ短篇小説」